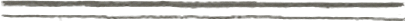古代の湖がもたらした奇跡の大地
9万年前から4万年前まで菊池から山鹿(やまが)にかけてサロマ湖に匹敵する湖が存在したという研究報告が存在します。
その研究によると4万年前に菊池から山鹿にかけて地殻変動によって盆地面が陥没し、台地上の水は引いたが、4万年前から縄文時代の終わりまでは、菊鹿盆地(きくかぼんち ※菊池から山鹿までの平野)は、湖水の中にあったそうです。
この湖を「茂賀の浦(もがのうら)」と言い、弥生時代になると次第に水が引き始めて、その範囲はだんだん縮小し、いち早く稲作の技術と鉄器の技術を持った人々が住み始め、肥沃な土地と生産技術と相まって強力な古代国家が築かれました。
もちろん当地も湖の中にあったことは言うまでもなく、昔は湖の中の島か湿地帯の中の微高地であったことを示す高島、松島、内島、戸田島、水島、平島、舟島、田島などの島のつく地名が現在も残っており、「茂賀の浦」の湖水が引き始めたころ、島だった頃の名残であると言われています。
現在、当地に肥沃な大地が広がり、良質な米が今もなお生産できるのは、湖の頃に蓄積された堆積物がミネラル豊富な土壌を築いたと考えられ、この恵まれた大地は、古代の湖がもたらした奇跡だと考えます。
当社は、この貴重な財産を絶やすことなく後世に残すためにも、自然の恵みに感謝し環境に配慮した取り組みを心掛けています。
↑ 菊池市から山鹿市にかけて存在した古代湖「茂賀の浦」